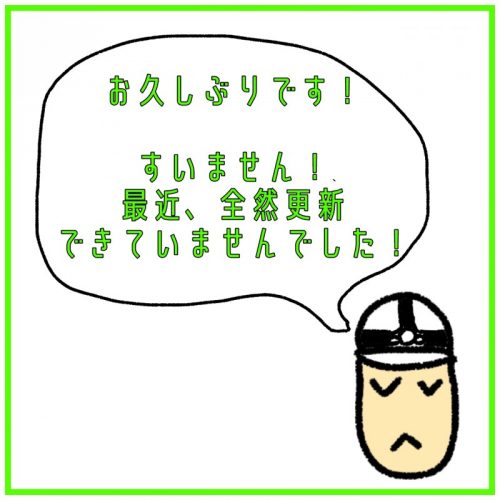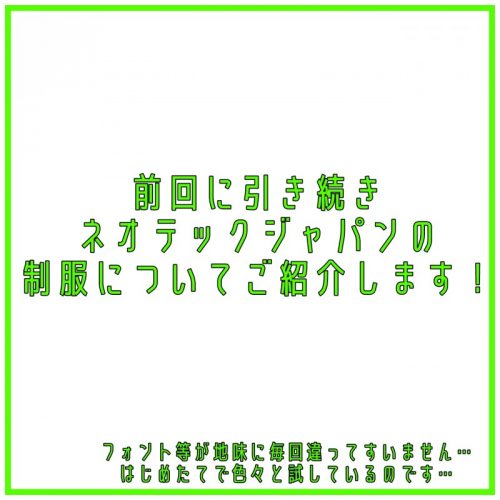Instagramのご案内🔨
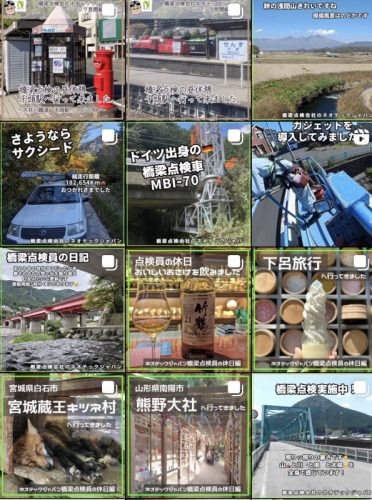
こんにちは!ネオテックジャパンです。
さて、ブログの更新がとても久しぶりになってしまいました💦
本日はInstagramのご案内をさせていただきます!
ネオテックジャパンのInstagramでは
●橋梁点検員の私達が見ている景色
●社員のオフの過ごし方
●会社のあれこれ取り組みなど
●出張中の美味いご飯
など等を発信しています!
定期的にInstagramを更新していますので更新を見ていただけると嬉しいです😆
よろしければ是非是非たくさんの方にフォローしていただければと思います!
ネオテックジャパンInstagram
https://instagram.com/neo_tech_japan?igshid=YzAwZjE1ZTI0Zg==